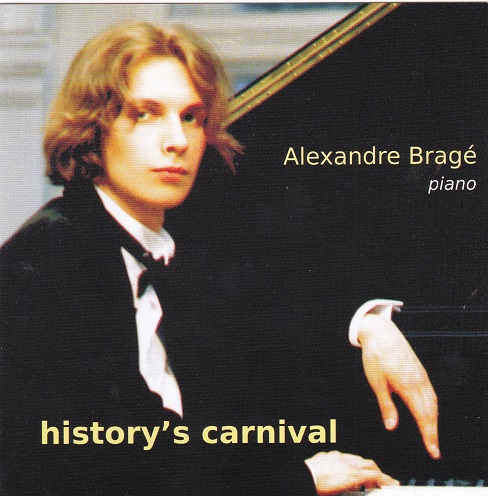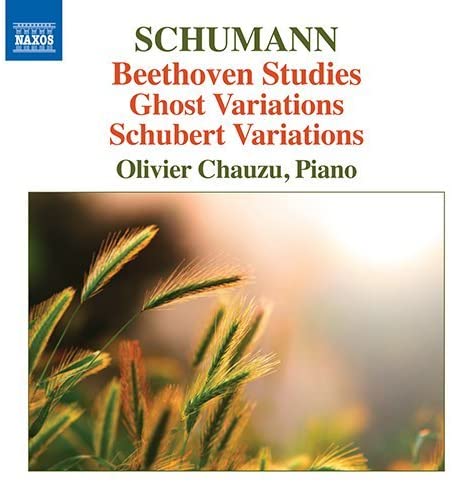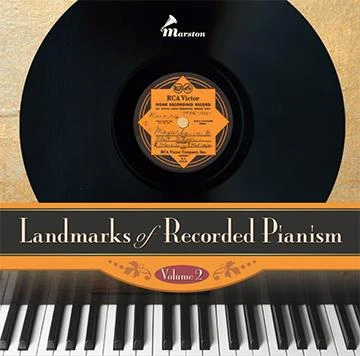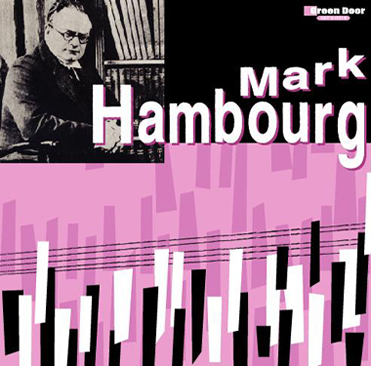(前回、アレクサンドル・ブラージェの弾くシューマンの謝肉祭の事を書いたら、この曲の演奏についていろいろ知りたくなってしまいました……)

この奇妙な譜面はシューマンの謝肉祭op.9の8曲目と9曲目の間におかれた「Sphinxes(スフィンクス)」です。Sphinxesといってもピラミッドの隣に座ってるのではなく、おそらくはなぞなぞに答えられない旅人を喰ってしまうギリシャ神話系の怪物の方です。シューマンは本当に困った作曲家で、Sphinxesは弾かなくてもよいとし(弾くな、とは言っていない)、仮に弾く場合はこの変な譜面をどう弾くのか全く指示がありません。謝肉祭の随所で使われまくる音列(しかも毎度おなじみ女がらみ)ではあるのですが、実際に弾いても曲らしい曲にはならず、まさに答えづらい謎。謝肉祭を弾くピアニストの多くは作曲者の提言通り、弾かずに済ませます。下手に答えたら喰われちゃいますからね。ただ、そもそも曲集全体で使われている音列の提示なら曲集の冒頭か最後にあってもよいのに、なぜ8曲目と9曲目の間にあるのかなどと考えたら、やはりこの場所にある存在意義としてここで弾いた方が良いのではないか、となる気持ちも生れ出づる悩みでしょう。実際のところ、弾かなくてもよい、と作曲家が言っているにもかかわらず、謎から逃げずに色々工夫してこの奇妙な譜面に挑戦する演奏家は沢山いました。
さて、便利な時代になりました。たとえば音楽配信サービスの中で曲の検索能力に長けているGoogle Play Music(GPM)で「Schumann Sphinxes」と入力すると、瞬時にして44種類ものSphinxesの演奏が出てきます(2020年4月20日時点)。曲が曲だけに44種類も聴くと暗鬱な気分になりますが、歴代のピアニストたちがどのようにSphinxesの謎に取り組んだがわかります。もちろんGPMにあるもの以外にも謝肉祭の演奏は沢山あるとは思いますが、とりあえずこの44種類を分類してみました。
| 分類 | 演奏者名(GPMの表記のまま) | 人数 |
| 楽譜通り 単音 |
ビレット、エマール、Passamonte、ル・ゲ、Chow、Jacquinot、Mazmanishvili | 7 |
| 楽譜通り 単音 内部奏法 |
Ciocarlie | 1 |
| 楽譜通り オクターブ拡大 |
ギーゼキング、Barere、コルトー、Slåtterbrekk、フィオレンティーノ、Uchida、Hagiwara、Pompa-Baldi、ローズ、ソコロフ、ペシャ、Strub、ラディッチ、Cabassi、Shamray、Siciliano、Kobrin、Kuschnerova、ニージェルスキ、ソフロニツキー、Schmitt-Leonardy、エゴロフ、ショアラー、Hautzig、マガロフ、アンダ | 26 |
| 楽譜通り トレモロ風オクターブ拡大 |
カッチェン、ガヴリーロフ、Hegedus、Callaghan | 4 |
| ラフマニノフ系 独自編曲 |
ラフマニノフ、スコダ、カルロス、ハミー | 4 |
| 独自編曲 | Schuch、コースティック | 2 |
録音史的に見れば初期の録音であるコルトー(1928年)はオクターブで弾き、ラフマニノフ(1929年)は作曲家ならではの独自の改変を加えてスフィンクスの謎に挑んでいます。弾かんでもいいというシューマンのいうことを聞いていない演奏家は昔からいたわけですね。
さて、この中で面白い(=変)なのは「楽譜通り 単音」に分類しているMazmanishvili。弦を直接叩く奏法を使っている可能性のあるような音ですが、1分30秒もかけてスフィンクスを弾きます。いくらなんでも音11個で1分30秒は長い。とりわけ3つの音列の間があまりに長い。謝肉祭全体の流れやバランスから見ても不思議な演出です。トイレタイムでしょうかねぇ。トイレに行って帰ってきてもまだ弾いてたって感じですけどね。同じ「楽譜通り 単音」ではエマールがピアノの響きを応用した面白い奏法を聴かせてくれます。
もはや禅問答?な現代音楽系アプローチも
さらにヘンなもの好きの私が注目したのは独自編曲に分類した2人。このうちコースティックの解釈は明解。なんにも弾きません。CDのトラック上は「Sphinxes」としてちゃんと5秒間存在してるのですが、なにも弾かないのです。謎は謎のまま、手も足も音も出ませんという面白い解釈です。ではなぜ5秒なのかという新たな謎と疑問がふつふつと沸き上がります。あえて無音にするならもう少し長い方が良かったかも。4分33秒やれとは言いませんが、5秒では単なるCDの曲間にしか思えませんからね。
もう1人はHerbert Schuch。彼は古典作品と現代作品を組み合わせたアルバムをいくつか発表しているのですが、謝肉祭ではSphinxesを現代作品風に仕立てて弾いています。最初の4つの音はエマールの単音アプローチにも似てますが、次の3音はピアノ弦を直接擦る内部奏法、曲の終わりの残響もペダルをわざとゆっくり離すことによる弦の音響変化を取り入れています。この改編はドイツの現代作曲家ラッヘンマンの響きにつながるものとして作られたそうです。ただ、シューマンの曲の真ん中でいきなりこの世界が始まることの違和感は相当なものです。音楽は何やろうと自由ですが、もともとが「貴女を想う音列3つから20曲もの曲集作っちゃいました(*)。凄いでしょ、こんなボクに惚れるでしょ。」という女がらみの自己顕示的かつ独善的な“謎”なので、こんなに時空を超えた拡大をしてしまうと、それこそ作曲者の意図である「狙ったオネエチャンのハートに届け」からは遠く遠く離れて行ってしまう気がします。ま、どうでもいいですけどね。大元が若者の単なる下心なので。
いずれにしろGoogle様のおかげでSphinxesの謎に対する44もの答えが月額980円であっという間に出てきます。Google様が検知しない答えはほかにもあることでしょう(ブラージェとかね)。けれどもひとまず44種もあれば、げっぷが出てお釣りが来ます。ほんといい時代です。ところで、シューマンの時代には、このSphinxesの謎に挑んだ人はどのくらいいたのでしょうか。ギリシャ神話のSphinxesは「朝は4本足、昼は2本足、夜は3本足、これはなんだ?」という問いを旅人に投げかけ、やがてオイディプスが「人間」という正解を出したら身を投げて自ら命を絶ったといわれています。まさかシューマンのライン川事件の真相は……???
《引用と補記》
* 謝肉祭の全ての曲にSphinxesの音列が使われているわけではない。Wikipediaの曲解説では20曲中18曲に使用されたとある。
参考CD:
・Schumann、Lagidze – Dudana Mazmanishvili (p) Cugate Classics CGC042 2017年
・ROBERT SCHUMANN – Michael Korstick (p) Oehms OC757 2011年
・Sehnsuchts Walzer – Herbert Schuch (p) Oehms OC754 2011年
【紹介者略歴】
吉池拓男
元クラシックピアノ系ヲタク。聴きたいものがあまり発売されなくなった事と酒におぼれてCD代がなくなった事で、十数年前に積極的マニアを終了。現在、終活+呑み代稼ぎで昔買い込んだCDをどんどん放出中。