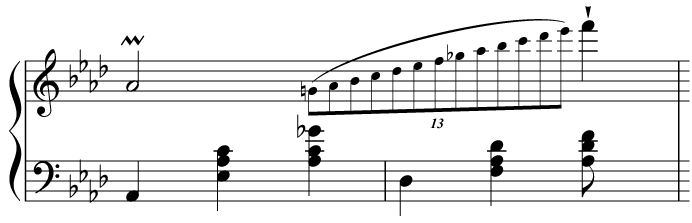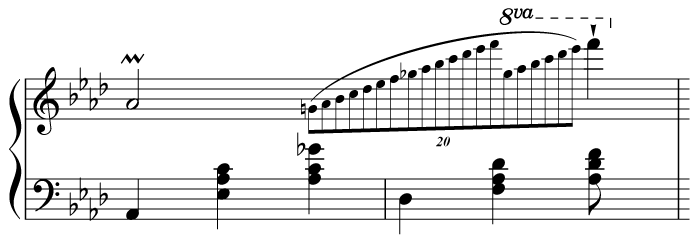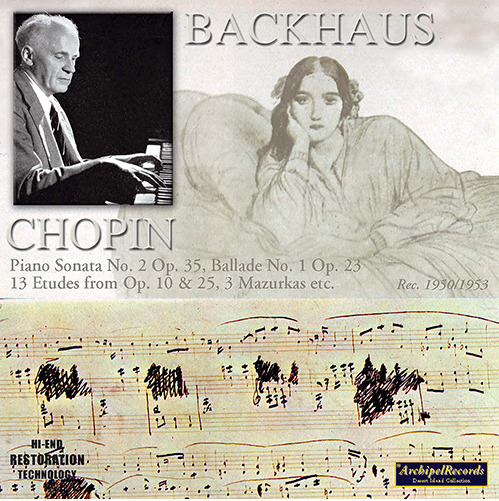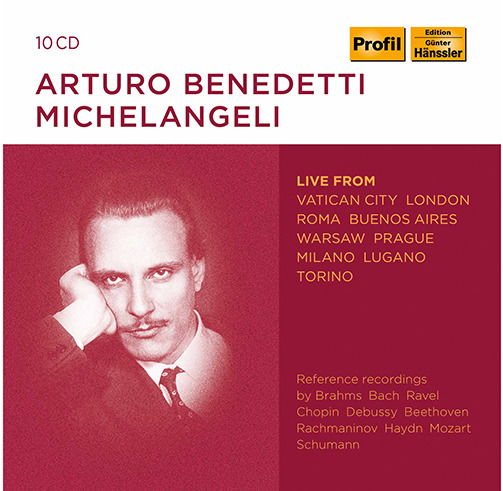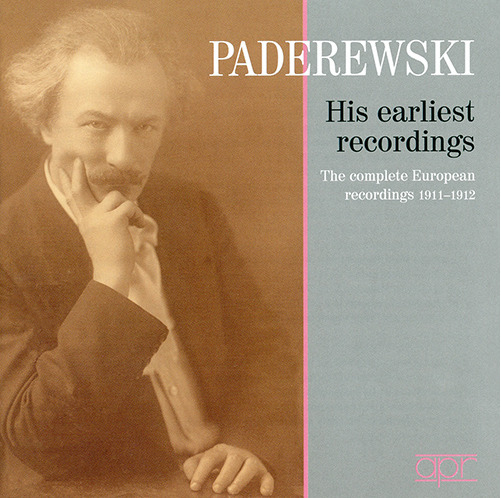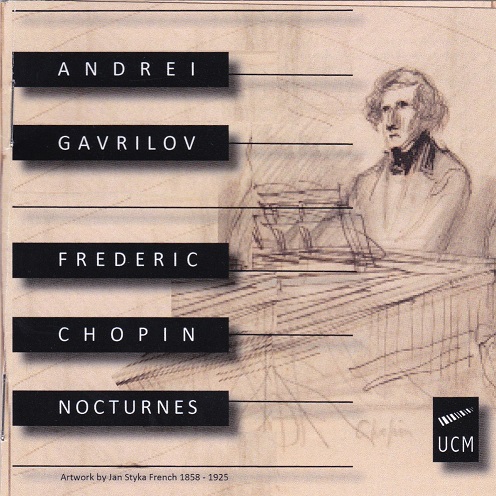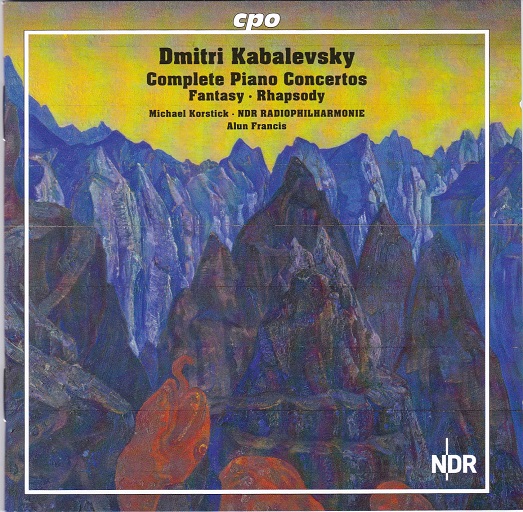文:高橋智子
1 1970年代前半の出来事と楽曲
これまでのフェルドマンの創作の歩みをごく簡単に振り返ってみよう。1950年代のフェルドマンは、ジョン・ケージを介して出会った抽象表現主義の画家や詩人たちとの交流の中から創作の着想を得て試行錯誤を重ねた。1960年代に入っても彼の創作はニューヨークを中心とする画家や詩人との交友関係が重要な役割を果たしていた。「For Franz Kline」(1962)や「De Kooning」(1963)は彼の友人でもある画家たちに捧げられた楽曲だ。1964年にはレナード・バーンスタイン指揮、ニューヨーク・フィルによって自身の楽曲が演奏され(第8回でとりあげたように、この演奏会の評判は芳しくなかったが)、「ニューヨークの気鋭作曲家」としての地位が徐々に確立されてきた。楽譜出版に関しては、1962年にフェルドマンはペータース Edition Petersと契約し、1950年代、1960年代のほとんどの楽曲はここから出版されている。1969年にフェルドマンはウニヴェルザール(またはユニヴァーサル)Universal Edition(以下、UE)と契約した。彼の最後の図形楽譜となった「In search of an orchestration」(1967)がUEから初めて出版された楽譜だ。以降フェルドマンの楽譜はUE[1]から出版されている。1970年代前半は出版社だけでなく、フェルドマンの周りの環境も音楽も大きく変わった時期である。
1970年代前半にフェルドマンに起きた主な出来事として、ヨーロッパでの評価の高まり、教師としてのキャリアの始まり、バッファローへの転居があげられる。1950年代、60年代に既にヨーロッパ各地で演奏や講演活動をしていたケージとデヴィッド・チュードア、そして彼のライバルだったカールハインツ・シュトックハウゼンとピエール・ブーレーズをとおしてフェルドマンの存在と音楽はヨーロッパでも注目され始めていた。60年代後半から特にイギリスの現代音楽界で注目され、1966年にフェルドマンはイギリスでの2週間の講演ツアーを行った。また、フェルドマンは1950年代後半頃から既にコーネリアス・カーデューとも親交があった。フェルドマンとイギリスの現代音楽界との関係が1970年代に入るとますます強まる一方、彼は地元ニューヨークに対する失望と苛立ちを見せるようになる。1973年に書かれたエッセイ「I Met Heine on the Rue Fürstemberg」[2]の中で、1950年代、60年代当時のニューヨークのシーンのやや閉じた雰囲気について回想している。
その時ヴィレッジ[3]で、私たちは一般的に世界にまだ知られていなかった芸術の何かを共有しているのだと感じていた。それは一種の袋小路だったが、それでも私はその気分を楽しんでいる。私は同時代の音楽を聴くことがほとんどできなかった時代に育った。もしもそういう音楽を聴くことができた人に出会ったなら、その人はその音楽に関わっている人だった。
We had the feeling, then in the Village, of sharing something in art that was unknown to the world at large. It was a kind of cul-de-sac, and I still enjoy the feeling. I grew up in an era when there was very little ability to hear contemporary music. And when you met someone who could, there was that kinship.[4]
このシーンの渦中にいた本人たちはそれなりに満足していただろうが、刺激や新しさの点でフェルドマンは物足りなさを感じていたのかもしれない。また、自分の音楽はもっと注目され、評価されてしかるべきという気持ちもあったのだと推測できる。そんな彼の苛立ちを少し和らげたのはイギリスの音楽界との接点だった。
私はほぼ同時にイギリスの知識層とアングラに注目された。1950年後半にはコーネリアス・カーデューに、1960年代前半はウィルフリッド・メラーズ[5]によって。
1966年から私は年に2、3ヶ月をイギリスで過ごしていて、おそらくバッファローの後にロンドンに行くだろう。イギリスの観客は他の観客とは違う。最高の雰囲気だ。私は変わり者だとまったく思われていない。
例えば1972年にB.B.C(訳註:BBC)で「The Viola in My Life」と「Rothko Chapel」のオーケストラ演奏に加えて、自分ひとりによる3時間の番組を2回行った。私はイギリスの音楽生活の一部となった。アメリカでは「音楽生活の一部」になるようなことはありえない。I was picked up in England by the establishment and the underground at about the same time. By Cornelius Cardew in the late fifties and by Wilfrid Mellers in the early sixties.
From 1966 on I’ve spent two or three months of the year in England, and I’ll probably go to London after Buffalo. They listen like no other audience. It’s the best atmosphere. I’m not really considered far-out.
In 1972, for instance, I had two three-hour one-man shows on the B.B.C.[sic], plus orchestral performances of The Viola in My Life and Rothko Chapel. I’ve become part of musical life in England. In America there’s really no such thing as “part of musical life.”[6]
ここでフェルドマンは、集団即興の可能性を追求していたカーデューをイギリスの「アングラ」、音楽批評家として同時代の音楽を積極的に紹介していたメラーズを「知識層」と位置付けている。自分の音楽がイギリスの実験音楽界隈と現代音楽界隈の両方で受容されていることにフェルドマンは満足げだ。当時、彼はロンドンにフラットの一室を借りていてロンドンのシーンに直接的に関わっていた。また、この頃の楽曲のいくつかはイギリスのアンサンブル・グループ Fires of Londonや作曲家アラン・ハッカーのグループ Matrixに献呈されている。[7]ニューヨーク以外の場所とのつながりや評価が増していくにつれて、フェルドマンのニューヨークに対する想いが冷めていく。詳しくは後述するが、このエッセイが書かれた1973年当時、彼は既にバッファローに転居していた。
ニューヨークとの接点を失ってしまった。私はいつもある種の部外者だったし、よい批評もされなかった。知ってのとおり、ニューヨークはパリと同じく現代音楽の街ではなかった。観客は忘れっぽく、作曲家についてもっと知ろうとする興味も抱かない。
(ニューヨーク・フィルハーモニックの指揮者としての)ブーレーズのプログラムは実験的ではない。むしろ予測できる反応とともに、どこかで最初になされた事例を華麗に示してくれる。
だから私は決まった音楽サークルに近づかなかった。実際バッファローでこうしていることが私にとっての初めてのアカデミックな状況だ。
革新的な作曲家と人々は言う。だが、私は常に大きな歴史意識、つまり伝統や継続性の感覚を持っている。I’ve lost contact with New York. I was always sort of Odd Man Out, not good reviews. New York, you know, was never a modern music city, any more than Paris. The audience has no memory, not interested in getting to know more about a composer.
Boulez’s programs[as conductor of New York Philharmonic]are not experimental. Rather glamorous samples of things done first somewhere else, with a known reaction.
So I didn’t come up through regular music circles. In fact, this thing in Buffalo is my first academic situation.
Radical composer, they say. But you see I’ve always had this big sense of history, the feeling of tradition, continuity.[8]
1950年末頃から数年続いたケージ、デヴィット・チュードア、アール・ブラウン、クリスチャン・ウォルフとのニューヨーク・スクールとしての活動、ジャクソン・ポロック、フランツ・クライン、デ・クーニングらとのクラブやセダー・タヴァーンでの芸術談義はフェルドマンにとってもはや過去のものとなり、心情的にも彼とニューヨークのシーンとの隔たりは1970年代頃から顕著になっていく。ニューヨークのシーンに対するフェルドマンの想いをさらに複雑にさせた出来事があった。それは1970年10月にニューヨークのマルボロ・ギャラリーで開催されたフィリップ・ガストンの個展だ。この個展が開かれるまでフェルドマンとガストンは親友同士だった。1950年から1966年頃までのガストンの抽象時代[9]の作品は、キャンヴァスに描かれたくすんだ色彩による微かなかたちを特徴とする。まるで何かの痕跡のようにも見えるガストンのこの時期の作品は、破線を用いて楽譜の中に音楽の痕跡を描こうとしたフェルドマンの自由な持続の記譜法に少なからず影響を与えたと推測できる。前回解説した「Between Categories」(1969)をはじめとする1960年代に書かれたフェルドマンのエッセイにガストンが度々登場し、フェルドマンの音楽における時間や空間の概念に大きな示唆を与えていた。1964年にはフェルドマンは自由な持続の記譜法によるピアノ小品「Piano Piece (to Philip Guston)」を作曲している。だが、2人の友情は1970年10月のガストンの個展をきっかけに、しかもフェルドマンから一方的に終わってしまう。[10]
マルボロ・ギャラリーで開かれたガストンの個展は主に1967年から1970年までに描かれた作品[11]で構成されていた。この頃からガストンは1950年代から1966年頃までの抽象とは全く異なる、具象というより漫画や戯画のような作風に転じる。この作風の変化がフェルドマンを大きく失望させ、彼はガストンとの友情にも終止符を打つ。この個展は当時どのように受けとめられたのだろうか。1970年11月5日発行の『Village Voice』に掲載された批評を見てみよう。
ガストンの新しい絵は漫画調で、変てこで、哀れで、社会的だ。頭巾をかぶって(KKK?)、切れ長の目をした人物がガタガタの車でうろつき、絵を描き、互いに殴り合い、たばこを吸う。時計、電球、指さし、ぶかぶかの靴は戯画化された姿で責め立ててくる。それはまるでデ・キリコが二日酔いでベッドに入り、アメリカが崩壊する話のクレイジー・カット[12]の夢を見ているようだった。過剰なのだ。彼のくすんだピンク色は私を打ちのめす強烈な絵画特有の色彩の流れとして、今もなお目に焼き付いている。だが、それは専らあやまちや恐怖による悲喜劇に寄与している。この変化をゲームの後半戦に持ってくるのは大変な勇気を必要とした。なぜなら、多くの人々がこれらをひどく嫌うのは自明だからだ。私は違うが。
Guston’s new paintings are cartoony, looney, moving, and social. Hooded (KKK?), slot-eyed figures rumble around in cars, paint paintings, beat each other, smoke cigars. Clocks, light bulbs, pointing hands, and out-sized shoes spoof and accuse. It’s as if De Chirico went to bed with a hangover and had a Krazy Kat dream about America falling apart. Too much. His smoky pinks are still in sight, as are terrific painterly passages that knock me out. But it’s all in the service of a tragi-comedy of errors or terrors. It really took guts to make this shift this late in the game, because a lot of people are going to hate these things, these paintings. Not me.[13]
この批評から、KKK(クー・クラックス・クラン)を彷彿させる白頭巾のキャラクターや漫画調の作風がフェルドマンだけでなく当時の多くの人々に落胆と衝撃を与えたのだと想像できる。ガストンと絶交状態にあったものの、フェルドマンは1980年にガストンが亡くなった際には追悼文を書き、1984年には長時間の楽曲の1つでもある「For Philip Guston」を作曲する。一方、ガストンは1978年に「Friend – To M. F.」のタイトルでフェルドマンのポートレートを描いており、この絵はフェルドマンの著作集『Essays』[14](1985)と『Give My Regards to Eighth Street: Collected Writings of Morton Feldman』(2000)の表紙に使われている。
この時期のフェルドマンと画家との関わりとして、マーク・ロスコとの交友と「Rothko Chapel」委嘱もあげられる。ロスコもフェルドマンと親しく付き合っていた画家の1人だ。キャンヴァス一面に色を塗り重ねたロスコの全面絵画といわれる様式は、フェルドマンが音楽の「表面」について思索するきっかけともなった。1965年、ロスコはメニル財団からテキサス州ヒューストンに建設予定の無宗教の礼拝堂[15](今日「ロスコ・チャペル」として知られている)に設置される壁画の委嘱を受ける。ロスコは1967年に礼拝堂の壁画を完成させるが、礼拝堂の完成を見ぬまま1970年2月25日に自殺。67歳だった。1971年2月27日のロスコ・チャペル建立を記念してメニル財団はフェルドマンに楽曲を委嘱した。フェルドマンは作曲に集中するため1971年春にデ・メニル夫妻が所有するフランスのポンポワンの別荘で過ごした。[16]その結果生まれたのがソプラノ独唱、混声合唱、室内楽による「Rothko Chapel」[17]である。この曲はフェルドマンの楽曲には珍しく叙情性にあふれた旋律が用いられており、その少し前に作曲された「Viola in My Life」1-4と同じ作品群と見なされる。
友人との別れも人生に大きな悲しみや変化をもたらすが、さらに直接的な環境の変化がフェルドマンに起こる。それは教師としてのキャリアの始まりである。1970年からフェルドマンは画家のメルセデス・マッターが創設したニューヨーク・スタジオ・スクール New York Studio School of Drawing, Painting and Sculpture[18]の学科長を務める。おそらくこれが彼にとって初めての教職のはずだ。以前、この連載の第1回と第6回でも少し触れたが、フェルドマンは家業の子供服工場を手伝いながら音楽活動を続けていた。フェルドマンが作業着姿でアイロンをかける様子を見た作曲家で指揮者のルーカス・フォスは1964年頃からフェルドマンのために大学のポストを見つけようと奔走していた。[19]その間、フェルドマンはドイツ学術交流会 DAADの奨学金で1971年9月から1972年10月までベルリンに滞在していた。ベルリン滞在時は「Cello and Orchestra」(1972)、「Voices and Instruments」(1972)など、編成がそのままタイトルとなっている楽曲が作曲された。
フォスの数年にわたる尽力が実り、1972年秋にフェルドマンはニューヨーク州立大学バッファロー校(以下、バッファロー大学)音楽学部作曲科のスリー教授 Slee Professor[20]に就任する。フェルドマンは約1年のベルリン滞在を終えるとバッファローに直行した。バッファロー大学教授就任に伴い、ついにフェルドマンはニューヨークを離れた。生まれも育ちもニューヨークで、生粋のニューヨーカーのフェルドマンはニューヨーク以外の街で暮らせるはずがないと思われており、フェルドマンのバッファローへの転居は当時、彼の友人たちをたいへん驚かせた。[21]マンハッタンの喧騒から離れたフェルドマンは新天地バッファローで作曲に集中し、これが結果として1970年代後半頃から現れる長時間の楽曲にもつながる。ニューヨーク以外の土地で無事にやっていけるのかという周囲の不安をよそに、安定した収入、快適な住居、そして何よりも学生や多くの一流の演奏家による演奏の機会を得たフェルドマンはバッファローでの暮らしを楽しんでいた。[22]当初フェルドマンの教授職は1年ごとの契約制だったが1974年には任期なしに変わり、ポストの名称もフェルドマン自らの希望でエドガー・ヴァレーズ教授 Edgard Varèse Chairとなった。
フェルドマンは大学で作曲を教えることについてどのように考えていたのだろうか。バッファローに移る直前の1972年8月にポール・グリフィスによって行われたインタヴューでフェルドマンは次のように発言している。
グリフィス:音楽教育に対するあなたの考えをぜひともお聞かせください。たしか、今年の夏にダーティントンのサマースクール[23]にいらっしゃる予定ですね。
フェルドマン:その予定です。音楽教育で非常に残念なことのひとつは、音楽教育が作曲家を生み出していないことです。1、2年前にとてもよい条件の仕事の話を断りました。なぜなら、教えることに対する私の考えは大学の学科で起きているようなものとは違うからです。自分の学生には演奏グループに関わってほしくないし、演奏のために作曲してほしくもありませんでした。
Griffiths: I would be interested to hear your views on music education, as I believe you are coming to Dartington this summer.
Feldman: Yes I am. Well, one of the tragedies of music education is that it doesn’t produce composers. I turned down a very good job a year or two ago, because my idea of teaching just isn’t what’s happening in departments. I didn’t want my students involved in performance groups, or in writing music for performance.[24]
ここでのフェルドマンは音楽教育、とりわけ大学で作曲を教えることに対して否定的な立場を取っているように見える。最終的に彼は教職に就くが、その直前まで大学での音楽教育には懐疑的だった。こうした態度の背景には、音楽院や大学ではなく、シュテファン・ヴォルペやケージらの私的なレッスンをとおして作曲を学んできたフェルドマン自身の経験が反映されているとも考えられるだろう。
グリフィス:では、音楽教育は何をすべきなのでしょう?
フェルドマン:音楽教育は専ら演奏家向けにすべきだと思います。作曲が教えられるべきものだとは思いません。今のアメリカで4人の最も影響力のある作曲家たち――私自身、アール・ブラウン、ケージ、実は古典学者だという理由でクリスチャン・ウォルフ――が音楽学科と一切関係せず、音楽学科での訓練も受けてこなかったことは興味深いです。私の態度はこう言えるでしょう。できる限り人間らしく全てをやり続けなさい。バランス感覚、作品に対して好ましい雰囲気、平穏さを作り出し、それらが必要な時に助けてくれる素晴らしい人々との関係を作ること。こうした事柄がもたらした一時的な関わり合いに対して彼らを密かに落胆させ、そしてそこから彼らを解放しなさい。なんらかのユートピアを作るのではなくて。
Griffiths: So what should music education be doing?
Feldman: I think it should just be for performers; I don’t think composition should be taught. It’s interesting that the four most influential composers in America today—myself, Earle and Cage, and Christian Wolff really because he’s a classicist—had no connections and no training in music departments. So my attitude is: keep everything as human as possible, create a sense of proportion, good atmosphere to work, quietude, fantastic people there to help when they need them, and let them quietly get discouraged and get out of this tentative commitment they made; rather than creating some kind of Utopia.[25]
音楽教育は作曲家ではなく演奏家に向けて行うべきというのがフェルドマンのこの時点での持論だったようだ。おそらくここでフェルドマンが問題にしているのは、音楽に関する技術や考え方というより、作曲家と演奏家との間に構築される関係性のことだろう。ある一定のコミュニティや場がひとたび構築されると、そこからなかなか踏み出せない。フェルドマンはそのような「ユートピア」に安住してはいけないと言っている。だが、このような発言を生んだフェルドマンの状況はバッファロー大学着任後に一変したように思われる。フェルドマンは、同時代の様々な上演芸術に特化した音楽学部の組織 The Center of the Creative and Performing Arts(以下、CA)での活動に精力的に取り組んでいた。当時、このセンターにはジュリアス・イーストマン[26]、ジャン・ウィリアムス[27]、デヴィッド・デル・トレディチ[28]らを中心とする気鋭の演奏家や作曲家たちが在籍していた。フェルドマンは彼らとアメリカ国内外へツアーを行い、バッファローを当時のアメリカにおける現代音楽の拠点のひとつにしようと力を注いだ。演奏会ではフェルドマンの作品だけでなく、他の教員や学生、ゲストとして招いた様々な音楽家の作品が演奏された。フェルドマンがバッファロー大学での音楽活動に大きく貢献したことは確かで、1975年6月には音楽祭 June in Buffaloを始める。この音楽祭はCAの後続組織 The Center for 21st Century Music主催でレクチャー、ワークショップ、演奏会を含む行事としてバッファロー大学で現在も毎年行われている。[29] 第1回のJune in Buffaloではフェルドマンのかつてのニューヨーク・スクール仲間である、ケージ、ブラウン、ウォルフの作品がとりあげられた。
着任前は「作曲は大学で教えられべきではない」と言っていたフェルドマンだが、もちろん実際は後進の指導に取り組んだ。バッファロー大学でのフェルドマンの著名な教え子としてバニータ・マーカス[30]とバーバラ・モンク・フェルドマン[31]の名前があげられる。1980年代に入るとフェルドマンはカナダ、オランダ、南アフリカ、ドイツ、日本など音楽祭やワークショップの講師を務めるようになり、行く先々で当時の若手音楽家や学生たちと対話を重ねた。例えばフェルドマンの講義録『Words on Music: Lectures and Conversations/Worte über Musik: Vorträge und Gespräche』[32]には、難解な比喩や音楽以外のエピソードを用い、時に受講生を困惑させながら自身の音楽観を説くフェルドマンのいくつかの講義が収められている。
次のセクションでは1970年代のフェルドマンの音楽の変化について解説する。
[1] Universal Editionのフェルドマンのページ https://www.universaledition.com/morton-feldman-220
[2] 初出は1973年4月21日発行Buffalo Evening News。本稿はフェルドマンのエッセイ集Morton Feldman, Give My Regards to Eighth Street: Collected Writings of Morton Feldman, Edited by B. H. Friedman, Cambridge: Exact Change, 2000に収録されているものを参照した。
[3] ここでフェルドマンが言っている「ヴィレッジ」はマンハッタン南西部のグリニッジ・ヴィレッジのこと。この界隈にはアーティストが集うクラブやバーが軒を連ねていた。
[4] Morton Feldman, “I Met Heine on the Rue Fürstemberg,” Give My Regards to Eighth Street: Collected Writings of Morton Feldman, Edited by B. H. Friedman, Cambridge: Exact Change, 2000, p. 116
[5] Wilfrid Mellers (1914-2008)イギリスの音楽学者、批評家、作曲家。http://www.mvdaily.com/mellers/
[6] Ibid., p. 117
[7] Morton Feldman Says: Selected Interviews and Lectures 1964-1987, Edited by Chris Villars, London: Hyphen Press, 2006, p. 43
[8] Feldman 2000, op. cit., p. 120
[9] ガストン財団 The Guston Foundationの作品カタログの時代区分に基づく。 https://www.gustoncrllc.org/home/catalogue_raisonne
[10] Feldman 2006, op. cit., p. 268
[11] ガストン財団のカタログでこの時期の作品を見ることができる。
https://www.gustoncrllc.org/home/search_result?search%5Btag%5D=Figurative 1968〜1972年代にかけてのガストンの作品に登場するKKKのキャラクターをめぐっては今日も主にレイシズムの観点から議論されている。ワシントンD.C.のナショナル・ギャラリーなど4つの美術館を2021年1月から巡回予定だったガストンの大規模な回顧展はBLMなどの社会機運を考慮し、展示内容を再考したうえで2024年に延期されることとなった。
National Art Gallery of Artの声明文https://www.nga.gov/press/exh/5235.html
[12] Krazy Kat 1913年から1944年まで新聞に連載されたコミック・ストリップ。
[13] John Perreault, “Art”, Village Voice, November 5, 1970
[14] Morton Feldman, Morton Feldman Essays, edited by Walter Zimmermann, Kerpen: Beginner Press, 1985
[15] Rothko Chapel http://www.rothkochapel.org/
[16] Feldman 2006, op. cit., p. 268
[17] フェルドマンの「Rothko Chapel」の概要は拙論参照。 https://geidai.repo.nii.ac.jp/?action=pages_view_main&active_action=repository_view_main_item_detail&item_id=435&item_no=1&page_id=13&block_id=17
[18] https://nyss.org/
[19] Ibid., p. 265
[20] Ibid., p. 270
[21] バッファローの音楽コミュニティ形成に貢献した、弁護士でアマチュア音楽家のFrederick Sleeと、その妻Alice Sleeからの寄付によって創設された教授ポスト。バッファロー大学には彼らの名前を付したSlee Hallもある。http://www.buffalo.edu/administrative-services/managing-facilities/planning-designing-and-construction/building-profiles/profile-host-page.host.html/content/shared/university/page-content/facilities/slee.detail.html
[22] Renée Levine Packer, This Life of Sounds: Evening for New Music in Buffalo, New York: Oxford University Press, 2010, p. 118
[23] Dartington Summer School https://www.dartington.org/about/our-history/summer-school/
[24] Feldman 2006, op. cit., pp. 48-49
[25] Ibid., p. 49
[26] Julius Eastman https://www.wisemusicclassical.com/composer/5055/Julius-Eastman/
[27] Jan Williams https://peoplepill.com/people/jan-williams
[28] David Del Tredici https://www.daviddeltredici.com/
[29] June in Buffalo https://arts-sciences.buffalo.edu/music21c.html
[30] Bunita Marcus http://www.bunitamarcus.com/index.html
[31] Barbara Monk Feldman http://www.composers21.com/compdocs/monkfelb.htm 1987年6月にフェルドマンと結婚した。
[32] Morton Feldman, Words on Music: Lectures and Conversations/Worte über Musik: Vorträge und Gespräche, edited by Raoul Mörchen, Band Ⅰ&Ⅱ, Köln: MusikTexte, 2008
高橋智子
1978年仙台市生まれ。Joy DivisionとNew Orderが好きな無職。
(次回は2月25日更新予定です)