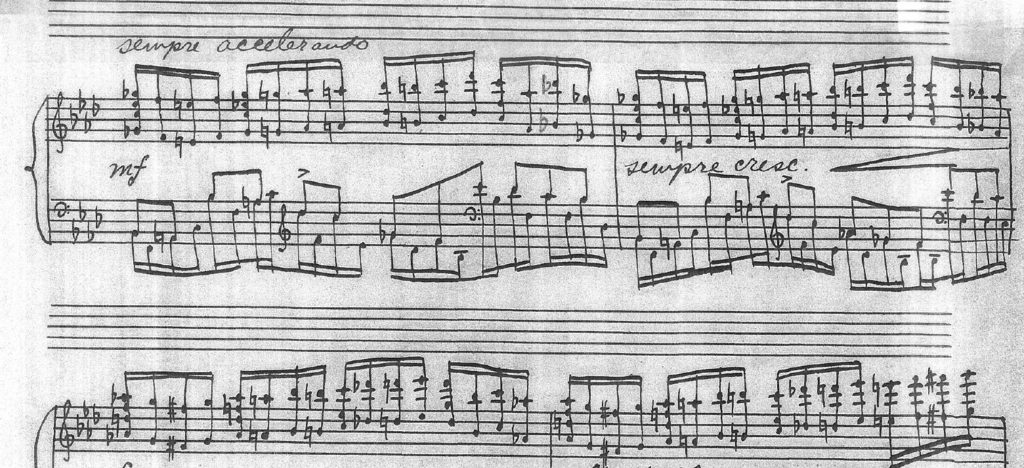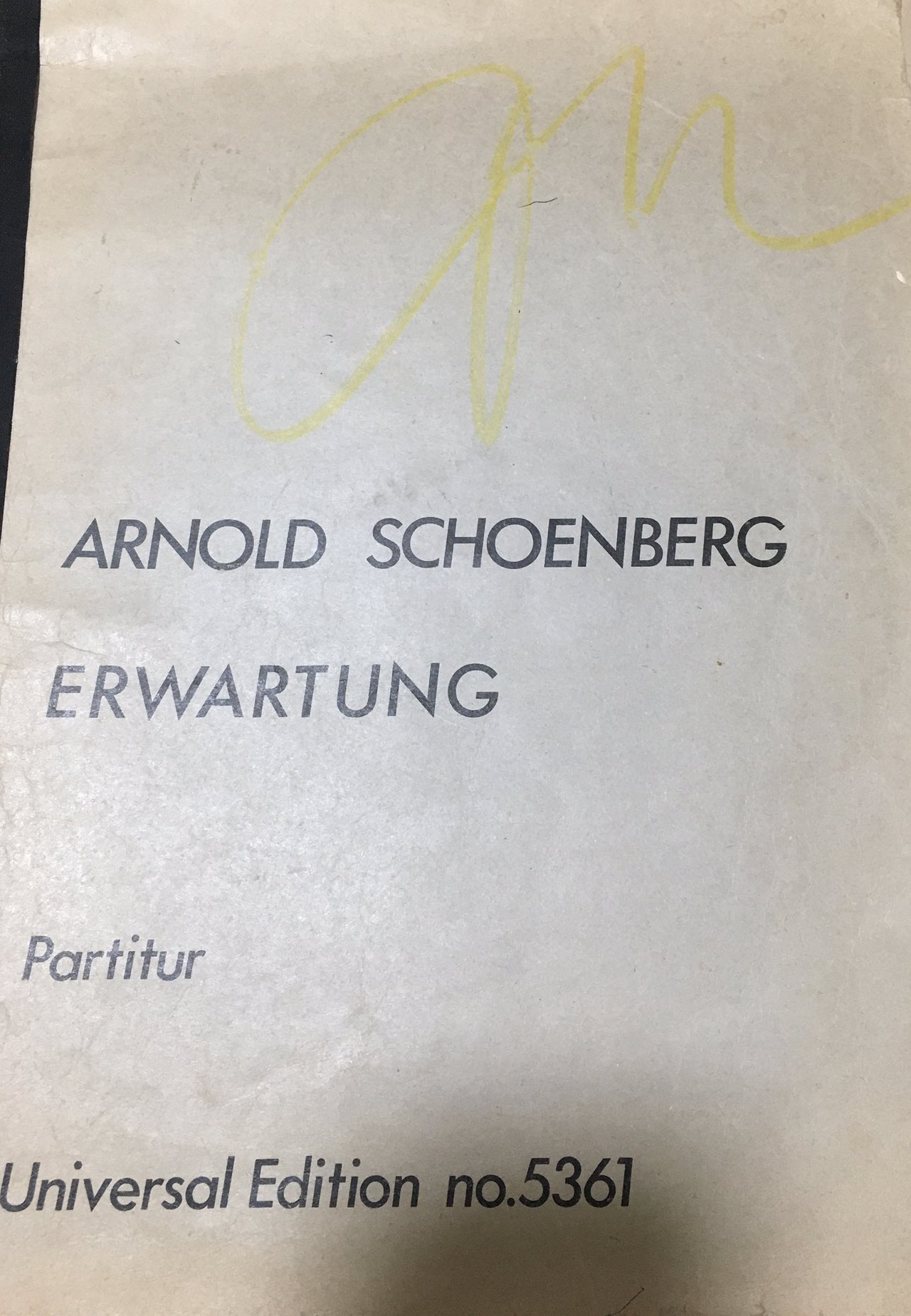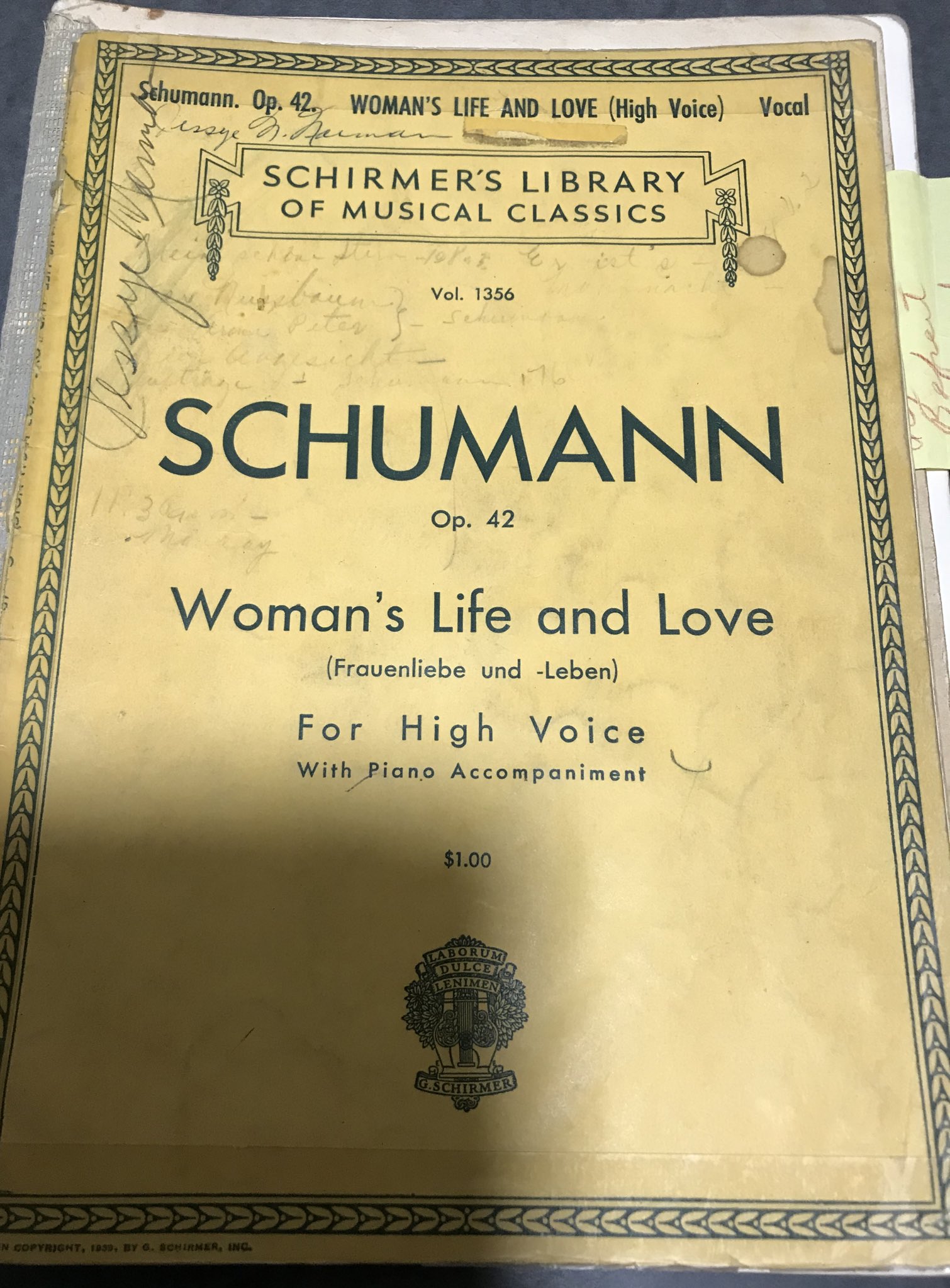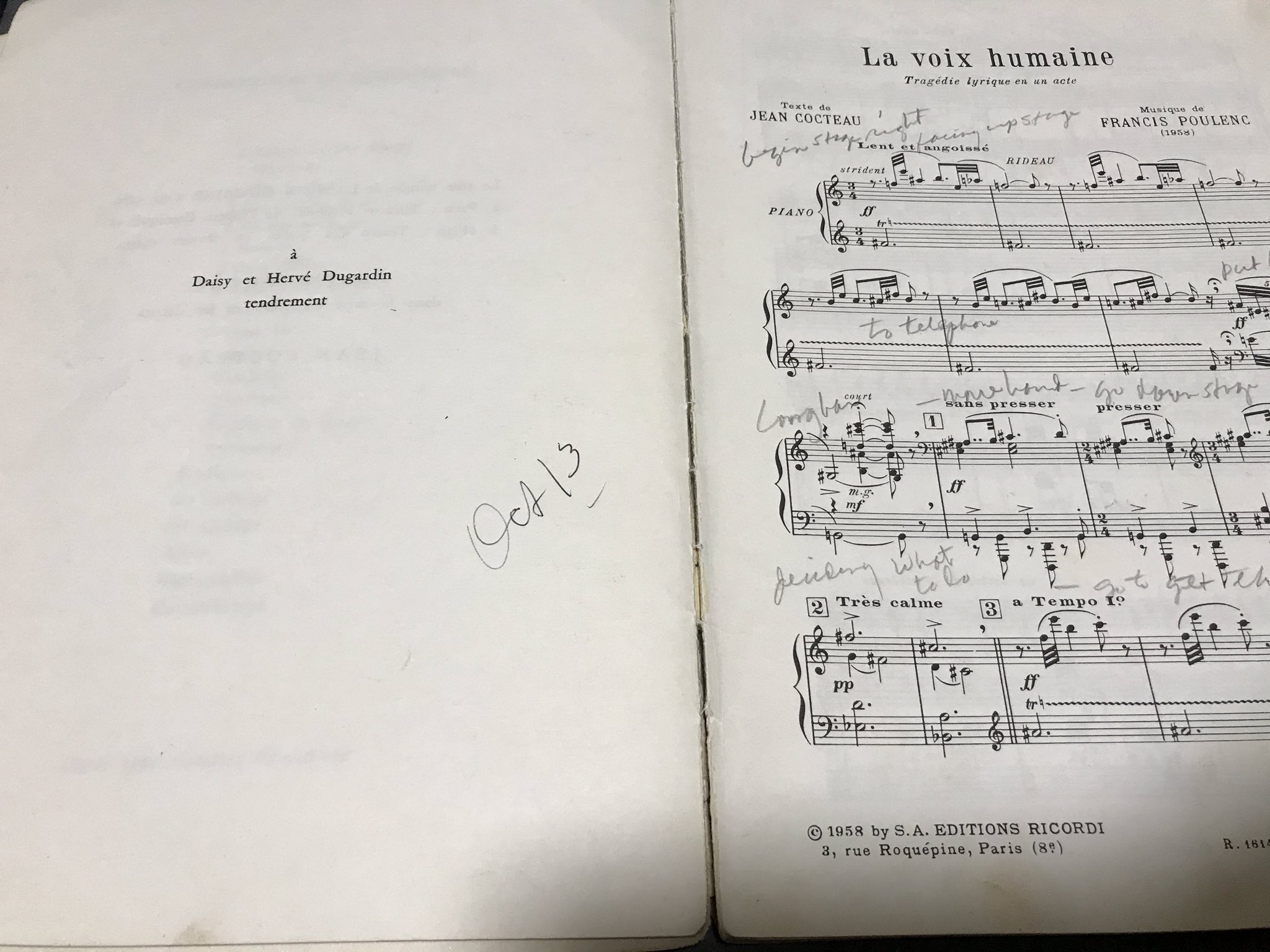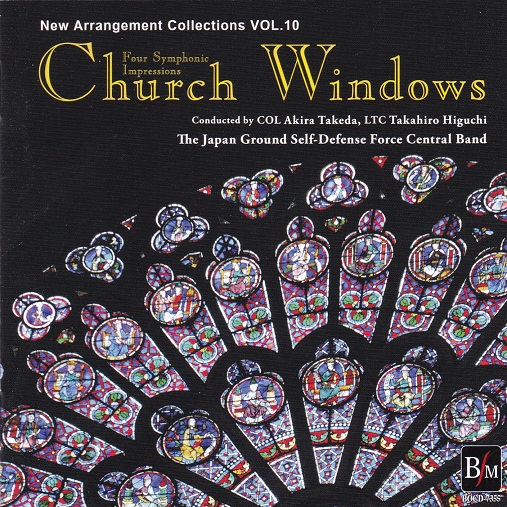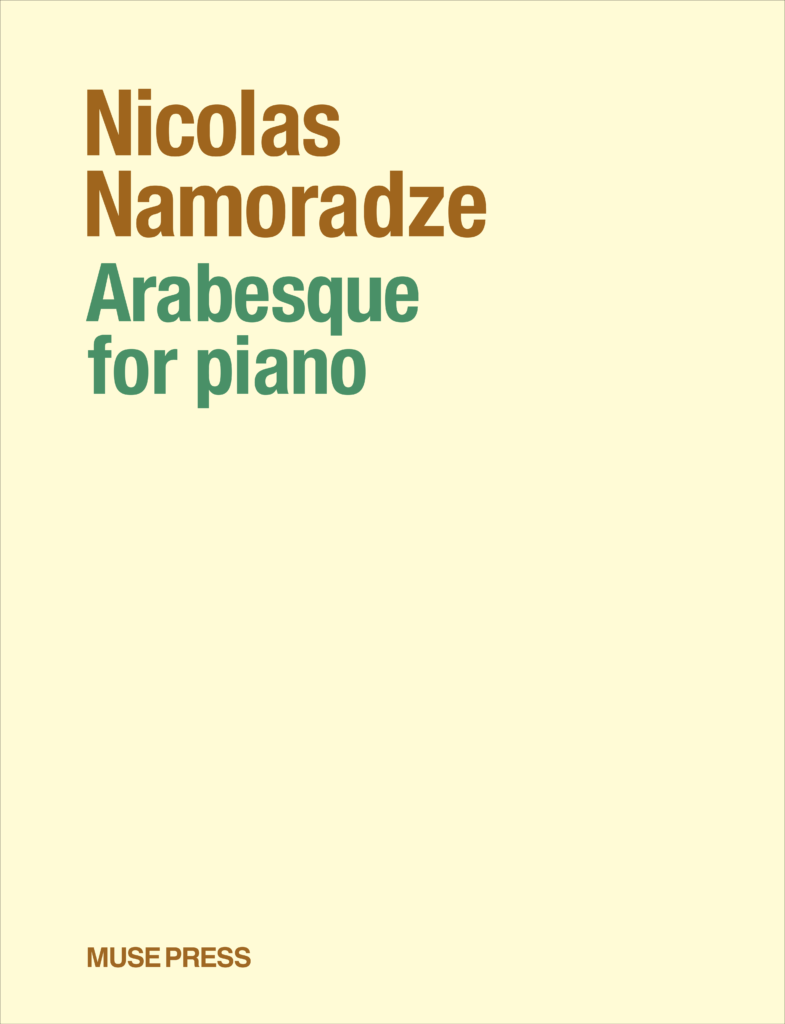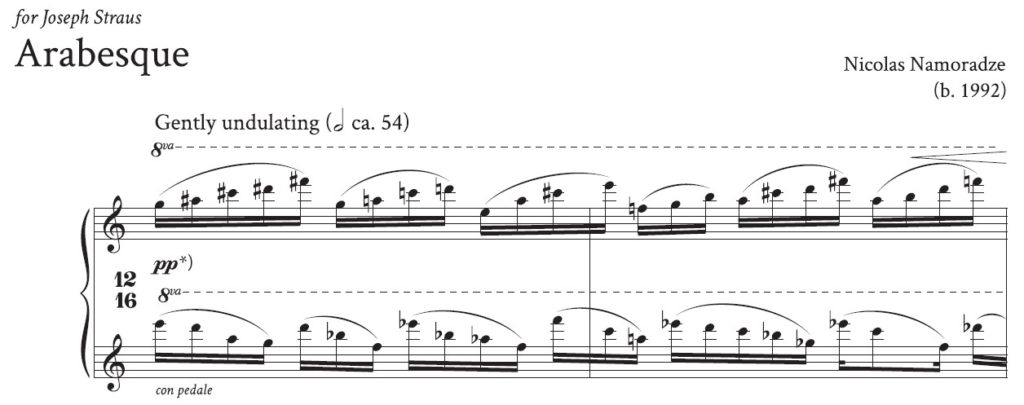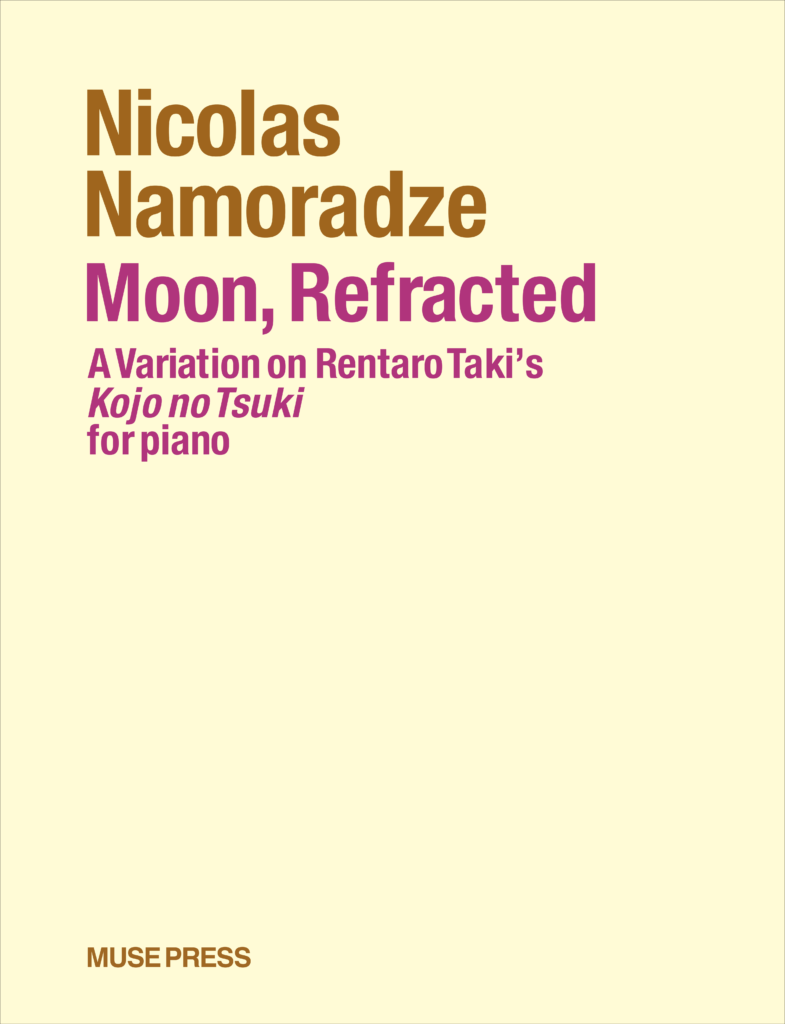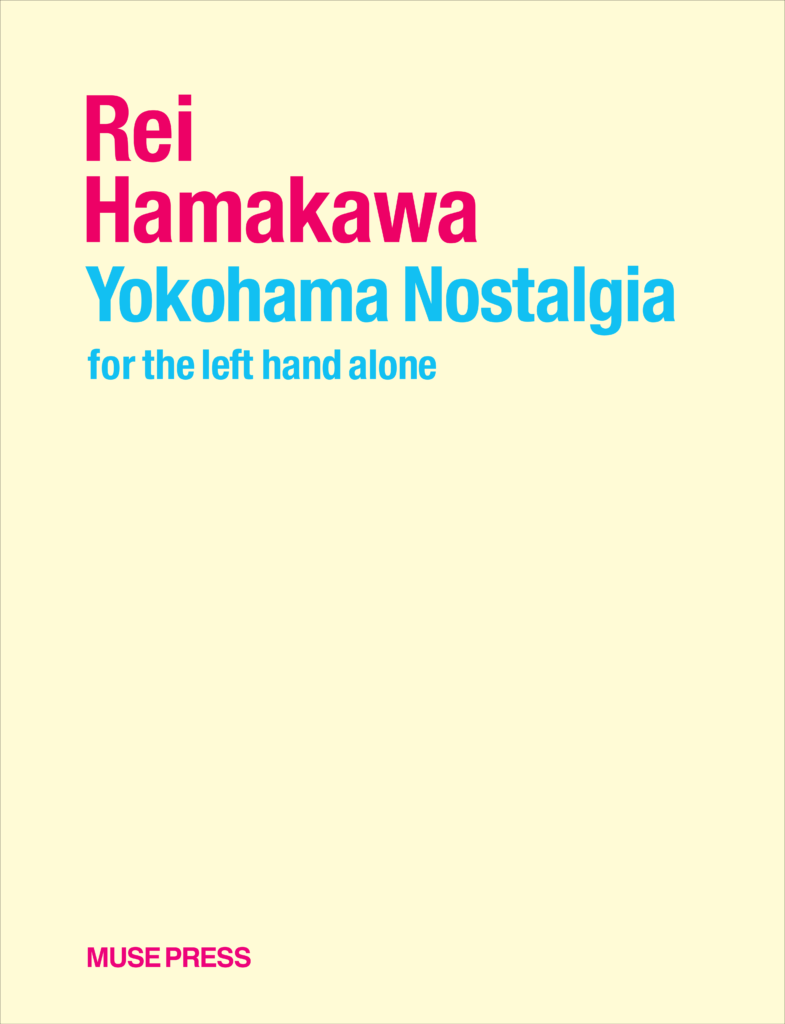12月の新刊情報です。発送は、12月16日頃より順次行います。
ピアニスト、指揮者、作編曲家として活躍する内藤晃によるピアノのための編曲作品が初出版となります。1点目はヨハン・セバスティアン・バッハが作曲した「G線上のアリア」のピアノ独奏版。内藤晃は、本作品の決定的なピアノ独奏版がないと考え、原曲の響きを忠実に編曲しました。指揮者としても活動する彼だからこそできた、オーケストラ作品をピアノに編曲する際の細かな配慮が散りばめられています。
J. S. バッハ/内藤晃:G線上のアリア(ピアノ独奏のための編曲)
税込1250円|菊倍|8頁
序文:内藤晃
2点目は、ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルトが作曲した大ミサ ハ短調 K.427 (417a)より「主は聖霊によりて宿り」のピアノ独奏版。このミサ曲は、結局は完成されませんでしたが、バッハと彷彿とさせるポリフォニックなテクスチュアをもつ意欲的な音楽で、当時のモーツァルトのバロックへの傾倒ぶりが滲み出ています。内藤晃は、2020年9月、友人の結婚披露宴で演奏するために本作品をピアノ独奏用に編曲しました。
モーツァルト/内藤晃:「主は聖霊によりて宿り」 大ミサ曲K.427(ピアノ独奏のための編曲)
税込1500円|菊倍|12頁
序文:内藤晃

ピアニスト、指揮者。東京外国語大学ドイツ語専攻卒。桐朋学園大学、ヤルヴィ・アカデミー(エストニア)などで指揮の研鑽を積む。ピアノ・指揮・文筆の多分野で活躍。訳書にA.ゲレリヒ著「師としてのリスト」(近刊、音楽之友社)、校訂楽譜に「ジョン・アイアランド ピアノ曲集」(カワイ出版)「ヤナーチェク ピアノ作品集」(ヤマハミュージックメディア)などがあるほか、音楽雑誌やCDライナーノートへの執筆も多い。その知的で美しい音楽づくりには、マリンバ吉川雅夫氏や作曲家春畑セロリ氏など、一流ソリストや作曲家から厚い信頼が寄せられ、彼らのCDでもピアノを担当している。自身のCDに「Primavera」(レコード芸術特選盤)「言葉のない歌曲」(同準特選盤)などがあるほか、2020年よりsonoritéレーベルを主宰し、レコーディング・ディレクターとしてCDのプロデュースも行っている。主宰ユニット「おんがくしつトリオ」では、教育楽器によるエキサイティングなアレンジが人気を博し、全国各地に招かれている。(公式ウェブサイト)