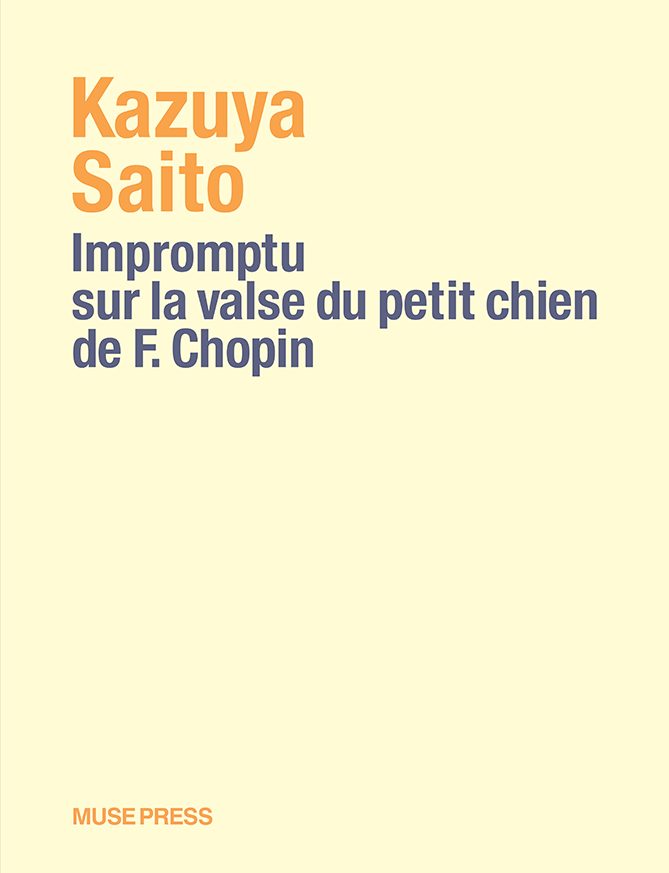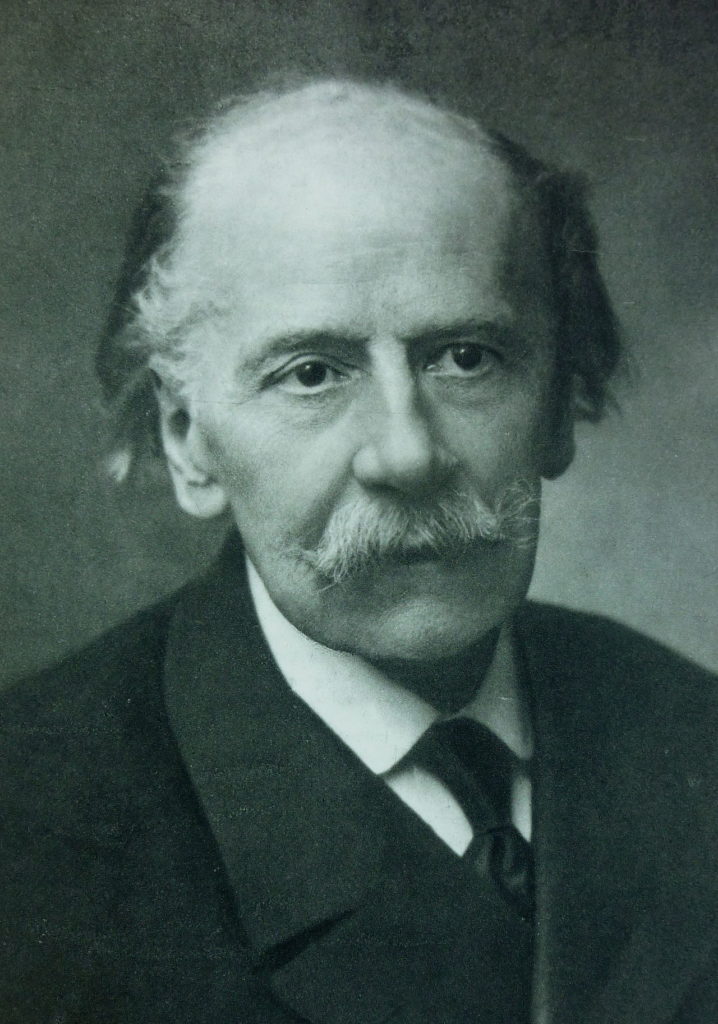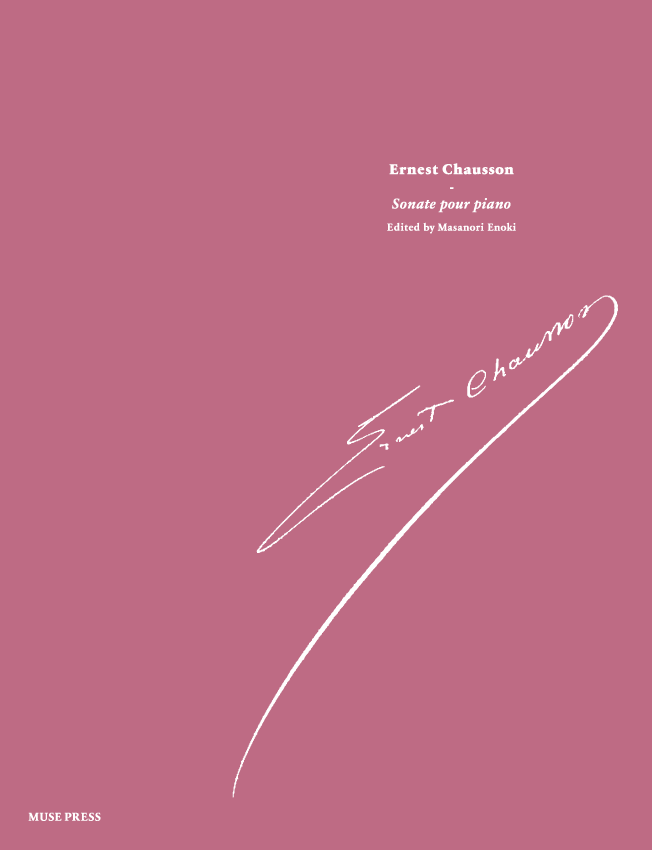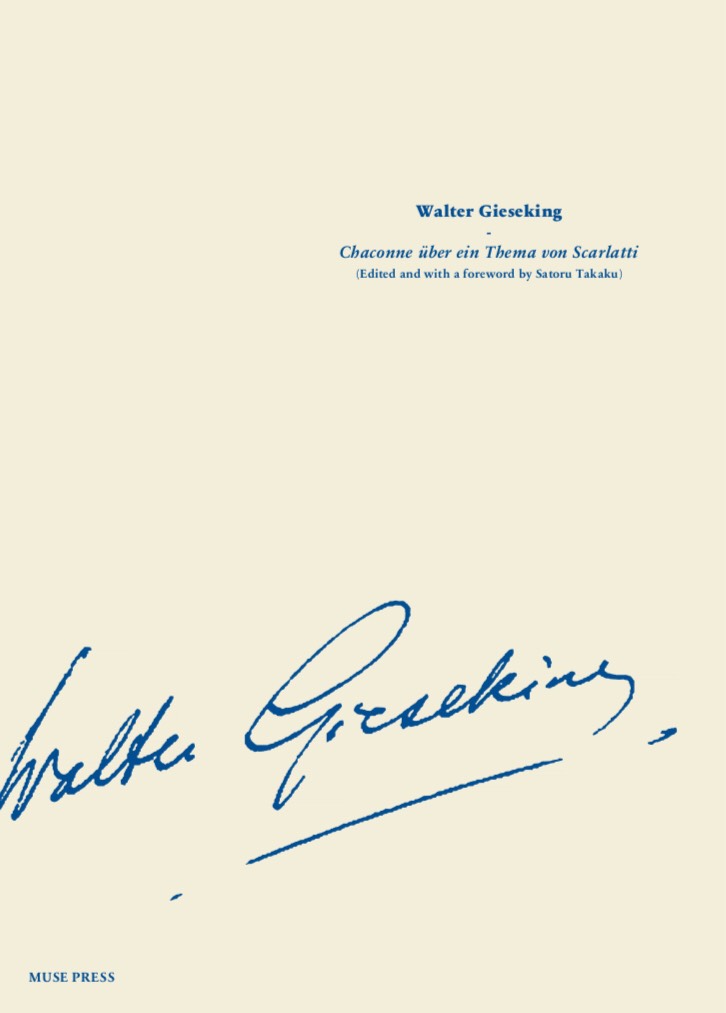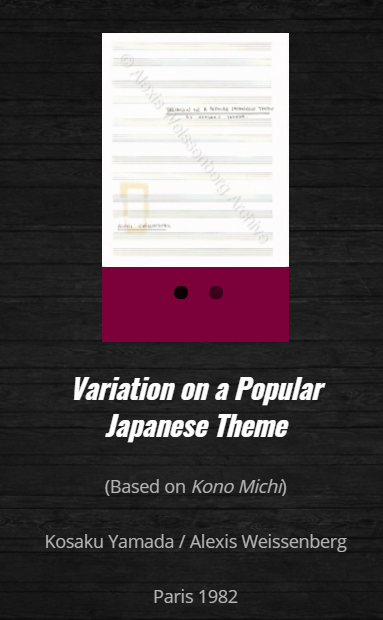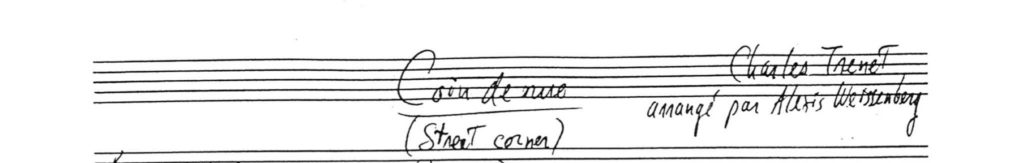文:高橋智子
2 ラジオドラマ「Words and Music」
おそらく1985年頃、フェルドマンは自身の2作目となるはずだったオペラを着想し、1977年の「Neither」と同じくサミュエル・ベケットに台本を依頼した。しかし、ベケットから断られてしまった。[1] フェルドマンの2作目のオペラ台本執筆の依頼を断ったベケットだったが、この2人は1986-1987年にラジオドラマ「Words and Music」で再び「共演」することになる。「Words and Music」は晩年のフェルドマンにとって最も大きなプロジェクトだ。
Continue Reading →